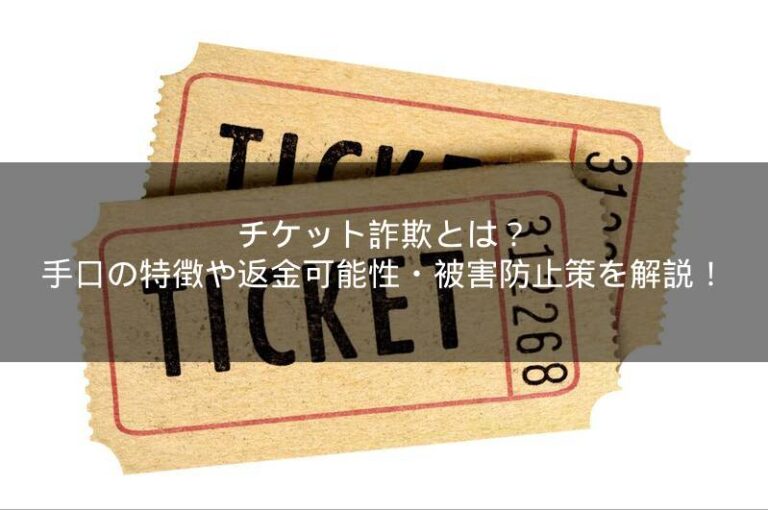「好きなアーティストのチケットをSNSで買ったのに送られてこない!」
「サッカーの観戦チケットをネットで買ったら偽物だった」
アーティストのライブや音楽フェス、人気のスポーツ観戦チケットをSNSなどを経由して購入しても、チケットが送られてこなかったり偽物であるケースが後を絶ちません。
そこで、本記事では「チケット詐欺」について手口の特徴や、返金の可能性、被害の防止策について詳細を解説します。
チケット詐欺とは?よくある2つの手口


正規ルート以外でチケットを購入する際には注意が必要です。
チケット詐欺とは、人気のライブやスポーツのチケットを不正に売買する行為です。
この章ではよくある2つの手口を紹介します。
チケットをSNSなどで購入したが送られてこない
人気のチケットを購入しようとしても、正規販売ルートではすぐに売り切れてしまうことがあります。
ファンとしてはどうしてもチケットを入手したいため、SNSなどで検索し、譲ってくれる人を探してしまいがちです。
しかし、SNSなどを経由する個人売買は詐欺の温床となっており、送金したのにチケットが送られてこないケースが多発しています。

購入したチケットが偽物だった
SNSなどで個人売買が成立し、送金した後に無事にチケットが届いても注意が必要です。
ライブやスポーツイベントの当日にチケットを持参したら「偽物」で、結局会場に入れないケースも多くなっています。
チケット詐欺かも?疑わしい3つの特徴
ファン心理を悪用するチケット詐欺が後を絶ちませんが、チケット詐欺には特徴もあるため、送金する寸前で被害を避けられる可能性もあります。
そこでこの章では、チケット詐欺に気付くための特徴を3つご紹介します。
送金・振込を急かす
チケット詐欺の特徴に「送金・振込」を急かしてくる傾向があります。
銀行やPayPayなどへの先払いを何度も要求してくる場合、詐欺の可能性があるため注意が必要です。
売却予定者の連絡先や氏名を控え、過去に同様の手口で詐欺を働いていないかSNSなどを検索してみましょう。
本来のチケット代金より極端に安い・高い
本来のチケット代金より極端に安い・高い場合も、チケット詐欺の可能性があります。
「あのチケットがこんな安い値段で買えますよ」
「プレミアが付いているチケットなので高騰していますが、お譲りできます」
こうした価格の設定は「転売ヤー」と呼ばれる転売者集団の特徴でもあります。
そもそも、2019年6月14日以降はチケット不正転売禁止法が施行されており、チケットの高額転売などが禁止されていることも押さえておきましょう。
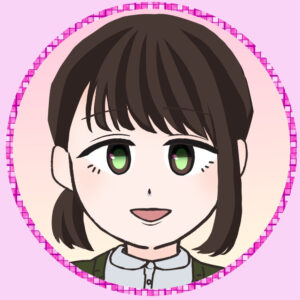
振込後連絡がつかない・既読にならない
せっかくチケットを見つけて銀行振込やペイ払いなどを行ったのに、その後音信不通となっている場合は、非常に高い確率で「チケット詐欺」の可能性があります。
やり取りをしていたLINEなどが既読にならない場合、すでにブロックされている可能性が高いでしょう。
チケット詐欺で返金してもらえる可能性はある?

チケット詐欺に遭ってしまった場合、返金してもらえる可能性はあるのでしょうか。
結論、チケット詐欺に遭ったまま放置していると、返金される可能性は低いでしょう。
返金してもらうためには、以下の対応を進めることが大切です。
- 相手に返金を求める連絡を行う(メールや電話などを利用し証拠も残す)
- 知っている相手の情報や、やり取りなどの証拠を持って、警察署へ被害届を提出する
- 送金口座を知っている場合は金融機関に凍結を依頼する
こうした対策を進めることで、返金される可能性は高まります。

チケット詐欺に遭わないために|4つの被害防止策とは

正規ルートでのチケット入手が理想ですが、どうしても観たいライブやスポーツのチケットがあると探してしまう人も多いでしょう。
そこで、この章ではチケット詐欺に遭わないためにできる、4つの被害防止策を紹介します。
1.取引相手の名前や連絡先を確認する
気になるチケットが見つかったら、個人売買に入り送金をしてしまう前に、まずは取引相手の情報を確認しましょう。
以下の内容をヒアリングし、メモに残しておくことが大切です。
- 取引相手の氏名、住所、電話番号
- LINEやX(旧Twitter)を活用する場合、スクリーンショットでやり取りを保存
- 銀行口座名や番号 など

少しでも違和感を覚えたら、取引は止めておきましょう。
2.過去の取引などを確認してトラブルを調査する
「●●というアカウントにチケット詐欺に遭いました」
「この人から購入したライブチケットが偽物でした。注意喚起します!」
チケット詐欺はSNS上で多発しているため、被害者が情報を公開しているケースがあります。
もしもSNSを介してチケットの個人売買を行う場合は、トラブルを起こしているアカウントではないか、確認しましょう。
極端に新しいアカウントは詐欺のために作られた可能性が高く、フォロワー数が0(もしくは少ない)の場合、詐欺のためだけに運用されている可能性が高いです。
3.急かされても慌てて送金しない
チケット詐欺の特徴にも挙げたように、チケット売買時に送金を急がせてくる場合は詐欺の可能性があります。
売り切れますよ、先払いじゃないと送りませんなどのセリフで急かされても、慌てて送金しないように注意しましょう。
先払いの場合、チケットが送られてこない可能性も多いため、後払いや対面式での売買がおすすめです。
4.偽のWebサイトやDMに記載されているURLにアクセスしない
チケット詐欺の中には、売買のやり取りから、偽物のWebサイトへ誘導されたり、DMに記載されているURLから入るように指示されることがあります。
こうしたサイトは「フィッシングサイト」の可能性があり、決済時に入力したクレジットカードや暗証番号などの個人情報が盗まれてしまうおそれがあります。
見慣れないサイトへ誘導されたら、サイト名で検索し詐欺行為の情報がないか確認することが大切です。
そもそも転売されているチケットは買ってもいい?

人気のアイドルのコンサートや、有名アーティストの引退ライブなどはチケットが高額転売されやすく、それでも購入しようとするファンは後を絶ちません。
では、転売されているチケットはそもそも購入してもよいのでしょうか。

チケットの高額転売は違法!
チケットの転売自体は違法ではなく、定価以下での転売はチケット不正転売禁止法では禁止されていません。
ただし、定価を上回るチケットは違法です。
転売目的でなければ、購入者はチケット不正転売禁止法では罰せられませんが、オークションやフリマサイトなどで転売されている高額チケットは違法に売られているものですのでご注意ください。
参考: 政府広報オンライン「チケットの高額転売は禁止です!チケット不正転売禁止法」
購入しても無効となる可能性がある
法律だけではなく、チケットに関する興行主側の規約にも注意が必要です。
チケット転売によるトラブルを防ぐために、興行主側が転売を禁止しているケースもあります。
転売チケットを購入すると、もしもライブやイベントが中止となってしまったとき、返金を求めても当初の購入者とは異なることを理由に、返金を認めない場合もあります。
個人間売買でトラブルなくチケットを購入でき、当日イベントへ持参しても、興行主側が「規約違反」と判断し、入場を断られチケットが無効となる場合もあります。
チケット転売の違法事例
実際のチケット転売による違法事例には、以下のようなケースがあります。
①繰り返しチケットを高額販売し、書類送検されたケース
2024年9月、東宝のミュージカルチケットを繰り返し高値で転売したとして、警視庁志村署はチケット不正転売禁止法違反容疑で、夫婦を書類送検しています。夫婦は1千万円以上売り上げていました。
参考:ミュージカルチケット転売疑い 売り上げ1千万円超、夫婦書類送検―警視庁 時事通信社会部 2024年09月03日 10時14分配信
②人気アイドルグループのチケットを高額転売し逮捕されたケース
2023年7月、アイドルグループが出演する公演のチケットなどを転売したとして、神奈川県警サイバー犯罪捜査課と川崎署はチケット不正転売禁止法違反容疑で、福岡市博多区の男性を逮捕しました。男性は同法が施行された2019年6月以降で総額約1億6千万円を売り上げていました。
参考:Snow Man チケット転売の疑い 売上げ1.6億円か 神奈川新聞 2023年7月6日 19時40分配信

安易な高額転売は控えましょう。
チケット詐欺に遭ったらどうすればいい?

もしもチケット詐欺に遭ってしまったら、一体どのように対処するべきでしょうか。
この章では詐欺発覚後の対応策をわかりやすく解説します。

警察へ被害届を提出する
送金後にもチケットが届かない、相手が電話やメールなどに応じない場合、送金やメールの履歴などを集めて、できる限り早期に警察へ被害届を提出しましょう。
LINEなどのSNS上でのやり取りもあった場合は、スクリーンショットを撮り、提出することがおすすめです。
口座の送金履歴なども役立ちますよ。
消費者ホットラインへ相談する
チケット詐欺は消費者ホットラインへの相談もおすすめです。
消費者ホットラインは電話で気軽に相談できます。
「これって詐欺なのかな?」と疑問に思ったら、問題点を整理するためにも問い合わせてみることがおすすめです。
消費者ホットラインを管轄する消費者庁では、チケット詐欺に関する情報も多く蓄積しており、仲介サイトの注意喚起やチケット詐欺の事例紹介なども行っています。
チケット転売を多く利用してる人は、消費者庁のお知らせを定期的に見ておくとよいでしょう。
| 消費者ホットラインの連絡先 | 受付時間 |
| 188
(全国どこからかけても、電話をかけた地域を管轄する消費生活センター、消費生活相談窓口へつながります) |
平日・午前8時30分から午後5時まで
土日祝・午前10時から午後4時まで (※対応窓口によって対応が異なる) |
参考: 消費者庁「チケット転売の仲介サイト「viagogo」に関する注意喚起」
弁護士に相談する
チケット詐欺に関する相談先は弁護士もおすすめです。
弁護士の場合、チケット詐欺を行った相手に対し、代理人として内容証明郵便を発送したり、少額訴訟を起こすことも可能です。
弁護士は刑事・民事の両面の手続きに精通しており、被害届提出についてもサポートできます。
まとめ:チケットの購入は慎重に!被害に遭ったら弁護士に相談しよう

この記事では、チケット詐欺について手口の特徴や返金可能性・被害防止策を詳しく解説しました。
チケット詐欺は身近な消費者トラブルであり、もしもの時は警察や消費者ホットラインへ相談しましょう。
しかし、記事内で紹介した通り、怪しいURLに個人情報を入力しないなど、事前の対策も大切です。
チケット詐欺のお悩みは、詐欺に強い弁護士へのご相談も是非ご検討ください。